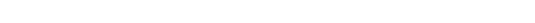アートは人間の問題、誰がどう見ているんだ、ということが重要になってくる
布施英利
見ている皆さん方が作っている、ということです
養老孟司
ヨコハマトリエンナーレ2017「島と星座とガラパゴス」
公開対話シリーズ「ヨコハマラウンド」ラウンド1
<0と1の間にあるアート> 養老孟司、布施英利対談より
言葉は、「同じ」という能力がないと、絶対に使えないんです
養老孟司
布施英利:お話を伺っていていろいろ思ったのですが、「アートというのは、コピーではない」というお話のくだりでこんなエピソードを思い出しました。ピカソが電車に乗っていた時に、「ピカソさん、あんたの絵はわけが分からない」とある男性に話しかけらたんですね。「じゃあ、どういう絵がいいんですか」とピカソが聞いたら、「こんなふうに描いたらいいんです」と奥さんの写真を見せるので、それに対してピカソが何て言ったかというと、「へえ、あなたの奥さんは随分小さくてペラペラなんですね」って。
つまり、ピカソにとって絵というのは「イメージ」ではなくて、まず「物」なんです。だから、それは写真のようにコピーできるものではない。では、物というのは何かというと、例えば大きさの問題というのがあって、絵のサイズです。複製にするとサイズというのは自由自在に大小変形できるのですが、絵にとってサイズというのは、場合によったら大事です。
ギュスターヴ・モローという近代の画家がいますが、私はパリにあるモローの美術館で、彼について書かれた本を読んで驚いたことがあります。モローはレオナルド・ダ・ヴィンチの研究をしていたのですが、何をしたかというと、ルーブル美術館に行ってダ・ヴィンチの《聖アンナと聖母子》(1508年頃)が描かれたキャンバスの縦と横のサイズを測り、それと同じサイズのキャンバスを作って絵を描いたというんです。描いている絵はもう全然ダ・ヴィンチと関係ない絵で、つまり、モローがダ・ヴィンチから何の影響を受けたかというと、サイズだけなんです。でも、多分、モローにとってそれはとても重要なことで、絵というのはある風格を持ったサイズみたいなのがあるんだろうなと思うんです。
さきほど、養老先生のお話の中で「(黒いマジックで)白と書いて、これは黒だろう」というのがありましたが、同じようなことをしているアートがあります。パイプを描いて、そこに「Ceci n'est pas une pipe/これはパイプではない」という言葉が書き込まれたマグリットの絵です。パイプの絵を描いておいて「パイプではない」という。パイプという視覚的なイメージを言葉で否定できるわけで、これはやっぱり「白と書いて、黒だ」というのと似ているわけです。
養老孟司:言葉というのは、「同じ」という能力がないと絶対に使えないんです。パイプというのは、実際にはいろいろなパイプがあるはずですが、言葉にすると全て「パイプ」になるです。
皆さん、英語を習う時に、冠詞が出てきますよね。例えば、「ジ アップル(the apple)」と「アン アップル (an apple)」。この違いを説明ができる人って、少ないんです。言語というのはできてから時間が経っていますから、不純なものが入ってしまうのですが、本来は「アン アップル」というのは概念のリンゴで、頭の中にあるものです。どんなリンゴなのかは分からないけど、リンゴだということは誰でも分かっている。一方で「ジ アップル」というのは感覚でとらえたリンゴです。この場合、常に具体的なリンゴ、感覚から入ってくるリンゴに使われるので、「そのリンゴ、このリンゴ、あのリンゴ」と具体的になるんです。
言葉というのは、みんなが同じことを考えているという前提に立っているんです。だから、「リンゴ」だと問題が起こりにくいんですが、「正義」とか「公平」とか「民主的」という言葉になると大ゲンカになるんです。それは、みんながそれぞれの頭の中で考えていることは違うのかもしれないけど、同じにしないと言葉というのは成り立たないからです。私たちは「同じ」ということに、暗黙のうちに寄りかかって言葉を使っているんですね。
アルタミラの洞窟画を見て、そこに言語や文字が隠されていると思ったんです
布施英利
布施:今回の「横浜トリエンナーレ」は、テーマとして「星座」というキーワードがあります。星座というのは、感覚で見れば、散らばっている点々の集合ですが、そこに熊とか白鳥とか、場合によっては物語までをも読み取らせてしまう。私が養老先生の助手をしていた30年ほど前、先生はよく「人類の始まりにおいて、星座というものが重要な役割を果たしていたのではないか」と仰っていましたね。
要するに、文字というのは歴史時代に入ってから生まれたわけですが、3万年から5万年ぐらい前の人間の脳は、一応、私たちと同じわけですよね。とすると、文字というものが存在しない歴史時代まで、文字や言葉の認識を司る脳の部分が退化せずに温存できたのは何か理由があって、養老先生はそれが星座なのではないかと。星座=文字ということですね。
養老:星座の大きな特徴は、固定しているということです。そうすると、いつも同じものを見ることができますから、線でつないで、単純な図形が作れる。しかも、ヨーロッパやエジプトに限らず、マヤ文明まで、古代の人々は天文学をやって、夜空を見ているわけです。私たちの祖先は、相当前からそういうものを見て、文字や言葉の代わりにしていたのかもしれないと思います。
皆さん、星座って不思議だと思いませんか? 当時としても特殊な能力のある人だと思いますが、「どうして、あんなにややこしい形を考えるんだろう」と。やっぱり文字や言葉の代わりに使っていたのではないかなと思うんです。星座がもう少し単純化されて一般化されると、文字になるのではないかと。
布施:先史時代、クロマニヨン人が描いた洞窟壁画がありますよね。スペインのアルタミラの洞窟は本物は見ることができないので、複製した洞窟に入ったことがあります。洞窟の側面には何も描いていなくて、天井に牛や鹿、いろいろな動物がいるんです。
僕が天井に描かれた動物を見上げながら思ったのは、「これはもしかして星座なのではないか」と。私たちはあれを単なるビジュアルのイメージとして見てしまうのですが、クロマニヨン人以降、我々の脳が変わらないとしたら、あそこに言語とか文字とか、そういったものが隠されているのではないかと。文字言語に代わる星座です。
養老:面白いですね。我々が使っている言語は、聴覚言語と視覚言語が重なり合っていますが、もともとはもっと分離していたはずなんです。
漢字が典型で、古い漢字、つまり象形文字ですが、あれは漫画です。いろいろな例がありますが、例えば「象」という文字は、もとのかたちは象の格好をしているんです。現在の「象」という文字は、もとの漫画から見ると、お尻を着いて立ち上がっています。漢字は漫画性をどんどん失ってきたんです。
その理由を以前、書いたことがあるのですが、もとの感覚的な性質がひとつでも残っているものは、文字ではなくてアイコンで、例えば水面があって湯気が立っている温泉マークは文字ではないんです。なぜかというと、耳には分からないからです。視聴覚が平等に使えるものが「言語」だとして進化していく中で、目だけでしか分からない特徴は、文字から落とされていきました。そういう意味ではアルタミラの壁画は、視覚言語の典型です。逆に星座には、光の点以外は感覚的な最初の印象がありません。
布施:私の息子がいま現代美術をやっているのですが、2歳ぐらいの時に初めて絵を描いた瞬間をすごくよく覚えているんです。最初は殴り描きをしていたのですが、あるとき、逆三角形を描いて、「アイチュ」と言ったんです。そのときに具象画というのは、言葉が最初にあったのかなと思ったんです。
どういうことかというと、「絵」というものと、「言葉」というものを考えたときに、言葉のほうが高度で後から身に付くものと思ってしまいますよね。ところが逆だったんです。つまり、アイスという言葉を知って、アイスの絵を描いた。だとすると、もしかしたらクロマニヨン人たちも…。
養老:どっちが先かは、なかなか難しくて、多分、両方の能力が同時に発生しています。フランス人は音声言語こそ、言語の基本だと考えるんです。歴史を考えれば明らかに音声のほうが先ですからね。だけど、字を書くためには、紙もいれば、鉛筆もいるという話で、それは文明の後にならないと、なかなか手に入らない。仕方がないから音声言語が先行し、歴史的に文字が遅れたような形で実現されていく。
そう思えば、さっき布施君が言われたように、星座にしても、アルタミラの洞窟画にしても、文字の代わりに使われた可能性はありますよね。その辺は、今はもう失われていますが。だから、さっきも言いましたが、私は現代人間というのは、乱暴だなって思います。全員がスマホを使って、テレビを見て、いろいろなものを消して、同じにしていくのですから。

私たちは脳みそで世界を測っているわけではなく、根本は体なんです
養老孟司
布施:養老先生は、授業や講演会で絵をよく描かれますよね。でも、それが聴衆に笑われない時は「僕の絵が下手で、何を描いているか分からないときだ」って謙遜して仰っていましたけど、先生は絵が結構うまい。
養老:僕の絵はインチキで、写真を撮ってフォトショップでなぞっているんです。ただ、これをやると、自分が本当には物を見ていないというのが、よく分かります。
例えば花の写真を撮ったとします。それをなぞったら絵になりますよね。でも、きちんと描こうとすると、たちまち問題が起こるんです。触角のある花があって、写真で見ると暗くて、花弁の中がよく見えない。暗く描いてしまえばそれで済みますが、写真と同じになってしまいますから、やはり花弁の中の触角を綺麗に描きたい。そうしたら、もとの絵を持ってきて見ないと、どうなっているか途端に分からないんです。皆さんも、写真を撮って、それをなぞって絵にしようとしたら、見なくてはいけないところが落ちている。見えない所がものすごく見えてくると思います。
布施:先生は解剖学が専門なので、脳だけではなくて、体の話も少しできたらと思います。先日、『ファーブル昆虫記』を読んでいたら、蜂が芋虫の幼虫に針を刺して、自分の子どもの餌にするのですが、その殺したはずの芋虫、何日たっても腐らない。それはなぜかというのをファーブルが調べたら、ちょうど芋虫に致命傷を与える中枢にまで届かないところで針止まるサイズに蜂の体がなっていることを突き止めた、というのが書いてあったんです。その時に、知性とか理性というのは脳の働きですが、実は体というのも、虫を殺さずに生かしておける心とか、そういうものが関係するものなんだなと思ったんですが。
養老:僕が『唯脳論』(筑摩書房、1998年)で書いた本質は、よく誤解をされるのですが、「人間が世界を測るのは、体でしょう?」ということだったんです。抽象的な言い方ですが、「世界を測って物差しを測る」ということです。つまり、脳みそで世界を測っているわけではなく、根本は体なんです。脳も体の内ですから。しかも指の先まで神経が張り巡らされて、これがないとどうしようもない。
人間の能力というのは、丁寧に使えばすごいんですよ。例えば鋳物の熟練工は、ミクロン単位でその誤差を感知します。ミクロンって、1ミリの1000分の1です。そのくらいの範囲できちんと分かるみたいです。その細かさって、すごいんですよね。日本はかなりデリケートな文化を持っていて、感覚中心の文化だと僕はよく言うのですが、気がついていない方が多いのは、日本の近代が、そういうデリケートな文化をどんどん変えてきたからです。
布施:ダ・ヴィンチの《最後の晩餐》(1495年〜1498年)で、養老先生にぜひ聞いていただきたい話があります。ご存知のようにレオナルド・ダ・ヴィンチは画家であると同時に解剖学の研究もしていて、解剖のデッサンを200枚ほど残しました。そこから推察すると30体程の人間の死体を解剖したといわれていますが、ここでお話ししたいのは、前腕の尺骨(しゃっこつ)と橈骨(とうこつ)の話なんです。前腕というのは肘と手首の間ですが、そこに尺骨、橈骨という2本の骨が平行に走っています。皆さん、幼稚園で『きらきら星』を歌いながら、きらきらのところで手首を回したと思うのですが、あのとき、前腕の骨はどうなっているのでしょうか。養老先生には釈迦に説法ですが、親指が内側に回すのが回内で、外側に回すのが回外というのですが、つまり手首を回すというのは尺骨、橈骨がX状にクロスすることなんです。
それで《最後の晩餐》ですね。ドイツの詩人のゲーテはイタリアに旅行したときにこの絵を見て、「この絵に描かれた12人の弟子たちの手の動きが、あらゆるポーズの多様性を試みている」というような感想を書いています。しかしよく見てみると、キリストに向かって左側に描かれている弟子たちは、全員、親指が内側にある。つまり回内です。では、右側に描かれている弟子たちはどうかというと、全員、親指が外側にあるので回外です。この絵に描かれている人物たちは、あらゆる腕のパターンをしているように見えるのですが、橈骨だけを見ると左側にいる人物は平行で、右側にいる人物は交差しているんです。
さらに中央のキリストを見ると、右手が回内で、左手が回外。ようするに、両側にいる弟子たちの手首の動きに重なっているんです。まるで指揮者のように、「はい、こっちの人、回内、こっちの人、回外」って言ってるようでしょう? ダ・ヴィンチは、骨の動きだけで心のドラマを描き切っていて、そこにまた絵画としての驚くべき多様性と統一感がある。骨格がどうなっているかというのを知った上で、ダ・ヴィンチは描いているんですね。
養老:非常に面白いですね。回内・回外ができるのは、人だけです。ほとんどの動物はこの2つの骨がくっついているのでできません。ダ・ヴィンチも気づいていたのではないですかね? それが人の特徴だという。
布施:ダ・ヴィンチは計算しつくしていたと思いますが、一方、ジャン=ミシェル・バスキアという27歳で夭逝した画家は、子どもが書くような絵を描くんです。それを批判する人もいて、そうした批判に応えたインタビューが残っています。「自分は考えないで引いた線はない」と言っているんです。アーティストといわれる人は、1本の線にも必然を持って引いていると思うんです。
養老:さきほども言いましたが、文明の発展の中で「同じ」という意識が働く一方で、いかに感覚を維持するか、そのバランスですよね。私は、それがアートにいちばん出てくるんだと思うんです。感覚を無視すると、アートにならないので。
布施:その他に、いくつか似たようなテーマで質問を頂戴しました。まず、「コンピュータで意識は作れますか」。
養老:これは質問が曖昧です。なぜかというと、意識というのは定義がないんです。最近になって意識が科学論文として扱われるようになりましたが、今まで自然科学の世界には入っていませんでした。だからといって、物理学的にどう意識を定義したらいいのか。エネルギーだ、電気だ、磁気だと定義しても、定義するのは意識ですからね。学問というのは、全て意識の上に乗っているので、「意識」を問うということをずっとしてこなかったと思っています。ですから、「コンピュータが意識を持ちますか」という質問は、その辺から考えないといけないんです。
布施:なるほど。では次の質問。「人工知能は美術に影響しますか」「ロボットはアートを感じることができるようになりますか」。先ほど「体も知性だ」というお話がありましたが、人間のコピーとして人工知能やロボットを作るのなら、そこまでも再現しないとコピーにならないと思うのですが。
養老:今日話をしてきたまさに人間の感覚について、ロボットだったらセンサーですが、そういうものを作ったら、ロボットは人間と同じになりますか? という質問をされる方には、私は「あなた、生物を甘く見ていませんか?」と答えるんです。皆さん方の始まりって、0.2ミリの球ですよ。受精卵、覚えています? 0.2ミリの球が、どうしてこうなるんですか。
甘く見てはいけません、人間を、皆さん方自身を。生き物というのは、刻々、変わっているんです。コンピュータはそれこそ電源を切ったらそのままです。所詮、人間が作っているんですから、乱暴なものです。分解すれば金属、以上、終わり。人間は、大腸菌を作れないですからね。コンピュータは作れますから、大腸菌とコンピュータ、どっちが偉いか分かるでしょう?
布施:将棋も囲碁も、今はコンピュータが人間に勝ってしまうということですが、アートの分野ではどうなんでしょう。これは、いろいろなアーティストが、作品を通して問いかけていると思うのですが。
養老:アートにおいてコンピュータというのは、キャンパスとか絵の具とか、あくまで道具に近いのではないでしょうか。上手に使えばいろいろできるはずですが、あくまでも手段ですよね。
布施:コンピュータが道具だとなると、あくまで、あっち側にある道具ということですよね。となれば、アートというのは、こっち側にいる人間の問題だと思うんですが、例えば先ほどのトビケラが作った巣。あれはトビケラにとっては驚きでもないわけです。となると、それを見るまなざし。誰が見ているんだ? どう見ているんだ? ということが重要になってくるわけでしょうか。
養老:だから、偉そうに言えば、アートは皆さん方が作るんです。見ている方が作っているということです。見る人がいなきゃ、アートはないんですから。見る人が見れば、虫の巣でもアートになっているような気がするんです。
布施:セザンヌが「あなたは神を信じますか」と問われた時に、「信じていなかったら、絵なんて描いていないよ」と言ったそうです。無宗教と思われるセザンヌでさえも、神の眼差や神と対話する中で創作しています。虫は何に対して、なんでしょうかね。まさか、養老先生に対してでしょうか。私たちは、生み出されたものから、それが読み取れるから、「面白い」と私たちは言うのでしょうか。
養老:虫は、何を考えているんですかね? 虫どころじゃなくて、うちの猫だって、何を考えているのか、いつも思っています。
ヨコハマトリエンナーレ2017
公開対話シリーズ・ヨコハマラウンド
ラウンド1 <0と1の間にあるアート>
2017年1月15日(日)14:00-16:00
横浜美術館レクチャーホール
登壇者:
養老孟司
(解剖学者、東京大学名誉教授、ヨコハマトリエンナーレ2017構想会議メンバー)
布施英利
(美術評論家、解剖学者)